前言
情報・IT時代・・あらゆる情報が瞬時にして世界を飛び回り、誰もがその利便性を享受できるという近年の急速な発達は素晴らしいものです。
情報、ここでは今からさかのぼる事約1500年前、中国の情報手段の一つを紹介します。
後世に、あまねく、伝うるべき情報を崖や石版に刻し保存しました。求める者は、それを拓本に取り写し、毛筆で書写しました。自ら取拓する者もあり、職人に依頼する場合もあります。
そしてその対価は安易な金額ではありません。膨大な資金を要したのです。それらを入手できたのは一握りの階級でした。
ここで一つの拓本にまつわる寸話を掲載させていただきます。
文房雑抄 その1
上遊天柱下息雲峰山題字 橋本吉文
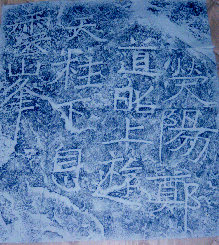 鄭道昭の書は山東省の雲峰山、天柱山、太基山等の摩崖に刻されている。清時代、考証学が盛んになると、これらの拓本を求める者は増えたが、山中の刻石のため、採拓は困難をきわめた。 鄭道昭の書は山東省の雲峰山、天柱山、太基山等の摩崖に刻されている。清時代、考証学が盛んになると、これらの拓本を求める者は増えたが、山中の刻石のため、採拓は困難をきわめた。『山左金石志』は、天柱山に拓本をとりに行き、転落する者がいたことを記載し、陸増祥(『八瓊室金石補正』)は、天柱山は険しい山であり、椎拓すること 極めて難しく、乾隆・嘉慶年間(1736-1820)の人達は見ることはできなかったと述べている。自らは、1874年6月、長沙市で鄭羲上碑を購入して いるが、この拓本は、数年前、大力なる者が巨費を惜しまず、崖に大網をかけ、勇壮な者に拓本をとらせたものという。 採拓の困難さは、費用に反映される。楊守敬(『激素飛清閣平碑記』)は、拓本をとるための足場、人、紙や墨の費用を計算すると、数十余部拓するのに百金 もかかり、拓するものは少ないという。しかし、拓本の価値が高まると、商品としての価値も高くなる。方若(『校碑随筆』)は、包世臣が著録で鄭書を評価し たときには見ることのできなかった拓本が、清末期にはは多くの人が手にすることができるようになった、これは、土地の者が利益を得ようと日々刻石を探した ことによると述べる。 執筆者・橋本吉文 大阪府立福井高校教諭 主な著書・書学大系(同朋舎) 中国法書選(二玄社) 共著 |
文房雑抄 その2
鄭羲下碑 橋本吉文
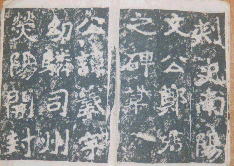 拓本の収集家は、少しでも古いものをと意識している。拓された時期が少しでも古ければ、刻石の破損が少ないからである。しかし、拓本のとりかたにより、文字の明瞭さが異なることがある。このことを葉昌熾(『語石』)は、刻石に草がはえ、苔むし、土が付いているものを洗わずに採拓すると良い拓はとれないと述べるとともに、刻面を掃除したあとの拓本は明瞭になり、単に古いだけで文字の不明瞭な拓本より値打ちがあるという。このように、刻された文字がはっきりするように刻面を掃除することを洗石といい、その拓本を洗石精拓本という。 拓本の収集家は、少しでも古いものをと意識している。拓された時期が少しでも古ければ、刻石の破損が少ないからである。しかし、拓本のとりかたにより、文字の明瞭さが異なることがある。このことを葉昌熾(『語石』)は、刻石に草がはえ、苔むし、土が付いているものを洗わずに採拓すると良い拓はとれないと述べるとともに、刻面を掃除したあとの拓本は明瞭になり、単に古いだけで文字の不明瞭な拓本より値打ちがあるという。このように、刻された文字がはっきりするように刻面を掃除することを洗石といい、その拓本を洗石精拓本という。鄭羲下碑には、洗石前の拓本があり、「未洗本」と称されている。西東書房から刊行された上田桑鳩蔵本がこれにあたる。 拓本を書学習の手本、考証学の資料として位置づける人は、洗石精拓本に対して高い関心を持つ。鑑賞の対象とする人は未洗本も味があると考えたり、現代では同様の拓をとることができないため、希少価値から求めるものもいる。人と異なる価値を持つものを求める収集家心理は複雑である。 刻された文字が風雨の浸食から磨耗し、岩肌と一体となる摩崖の拓本。その拓本から文字が浮かび上がる。そこに魅力を感じる人は多い、機会があれば原拓を観てほしい。編集者追補 伝わるところによれば、採拓職人は一定量の拓を取り終えた時、いずれかの文字を故意に破損させることもあったそうである。これは、自分の採拓本が後のものよりも文字が残っており価値がある、ということを狙った行為である。 |
文房雑抄 その3
大観帖 橋本吉文
 『大観帖』10巻は、『淳化閣帖』の諸問題を正す目的で作られた。徽宗皇帝の命により、内府に収蔵している真蹟などから直接写し取り、石に刻され、大観年(1109)に完成したもので、大清楼で行ったことから『大清楼帖』ともいわれる。 『大観帖』10巻は、『淳化閣帖』の諸問題を正す目的で作られた。徽宗皇帝の命により、内府に収蔵している真蹟などから直接写し取り、石に刻され、大観年(1109)に完成したもので、大清楼で行ったことから『大清楼帖』ともいわれる。宣政間(1111-1125)、法帖は流布する。しかし、靖康2年(1127)、靖康の変で金が開封を陥落すると、徽宗、欽宗の二帝以下3000人程が捕らえられ、財宝とともに、金の地に連れ去られた。このとき、『大観帖』の原石も持ち去られた。20年程で原石が失われ、10巻揃ったものは伝えられていない。 金と宋との間で互市場である場が開かれると金から『大観帖』が入った。その拓本を「場本」という。 翻刻本としては、金によるものがあり、第3巻の亮帖の「亮」字が刻されていないという。他に、元の顧徳輝、明の陳懿卜のものがあり、明のものは大正3年11月、西東書房から影印された。清代にも翻刻本があるといわれてきたが、これは明の『大宝賢堂帖』を用いた偽帖である。 図版のものは、金または元の翻刻本として書学書道史学会にて発表したものである。 |
文房雑抄 その4
印材 鴨雄緑 橋本吉文
 鴨雄緑が初めて図版で紹介されたのは、小林徳太郎著『図説石印材』 であった。その解説には、「古来『幻の石』としてほとんど絶無と云われた珍品中の珍品が唯一顆存在していた」という。この印材は菅原石廬氏が収蔵しており、淡光社から刊行された『篆刻入門』では、谷干城旧蔵品として紹介している。 鴨雄緑が初めて図版で紹介されたのは、小林徳太郎著『図説石印材』 であった。その解説には、「古来『幻の石』としてほとんど絶無と云われた珍品中の珍品が唯一顆存在していた」という。この印材は菅原石廬氏が収蔵しており、淡光社から刊行された『篆刻入門』では、谷干城旧蔵品として紹介している。この印材が珍品といわれる理由は何か、張俊勛の『寿山石攷』をみると、「洋緑」の項にて「寿山郷より界を隔つ十里の洋郷に産す、緑色閃通し、雄鴨の翼の如きものは佳。俗に鴨雄緑という。郷人風水に惑う。公に開鑿を禁ず。故に産を断つを致す」という。土地の人により産出が停止されたため幻の石印材となったのである。そのため、村上鬼空(『桃紅艾緑』)が「珍品中の珍品にして、其名今に存して實物は全く見るを得ず」といい、「今若し方五六分角のもの一顆あれば萬金も亦貴しとするに足らずといふに見るも以て其珍重の度を知るべきである」という。その実物が、日本において紹介されたのであるが、中国において言及されていないのが不思議である。 図版のものは、濃緑色のものであるが、太陽の光にかざすと斑紋の先端が蛍光色に光る。 |
編集者補追 話が見えない方へ
印材、俗に云うハンコの材料です。書画作品を制作し署名をします。これを落款といい署名して押印する行為を指します。作品を見た人に、どのような印材を使用しているのかは分かりません。同じようにどのような硯、筆、材料を使用しているのか分かりません。
これ正にマニアの世界なのです。どのようなアイテムにもマニアは存在するものです。
万人が感動する作品さえ書ければ、どのような材料を使用しても関係ない、と言う人もおります。
文責・藤尾博

